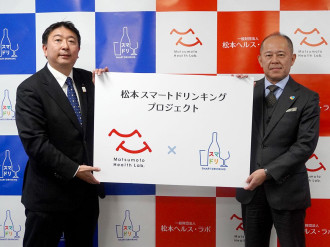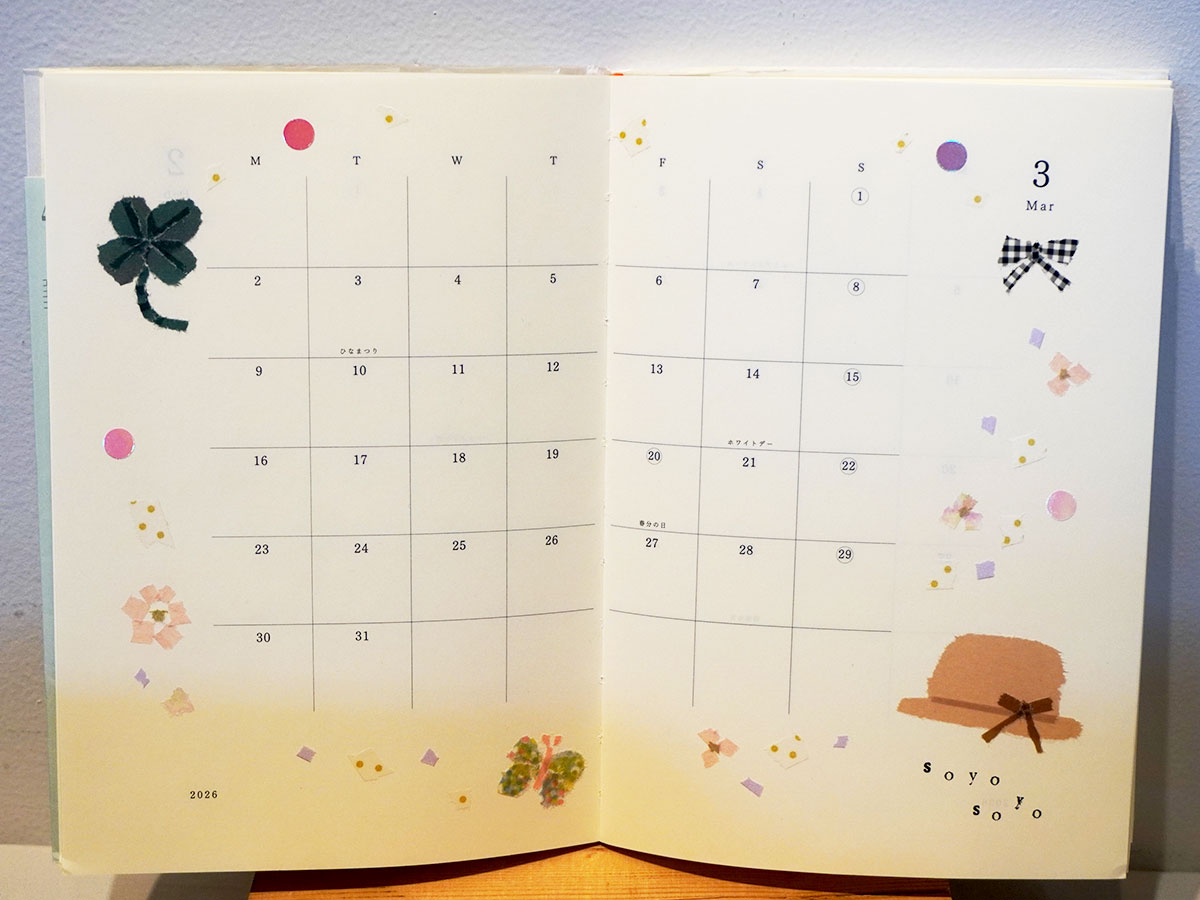「中部山岳国立公園南部地域×ウェルネスツーリズム」の可能性

提供:環境省 制作:松本経済新聞
北アルプス一帯を占める日本を代表する山岳エリアであると共に、温泉のある山岳地域ならではの標高差を誇るフィールド・中部山岳国立公園南部地域。国全体のインバウンド政策の一つとして、2016(平成28)年から、環境省が地域の自治体や事業者と連携して「国立公園満喫プロジェクト」を進めています。環境省中部山岳国立公園管理事務所では、温泉のほか多彩なコンテンツを組み合わせた滞在型旅行の一案として「ウェルネスツーリズム」に着目し、現地調査やモニターツアーなどを実施してきました。
国内におけるウェルネスツーリズム推進の第一人者として活躍する琉球大学の荒川雅志教授を招き、同事務所所長・森川政人さんと利用企画官・甲斐原さなえさんが、同地域の可能性を語り合いました。
目指すのは“日本型”ウェルネスツーリズム
荒川ウェルネスというのは、時代によって定義や概念は変わってもいいと思っているので、あまり固定化したくはないのですが、変わらないゴールとすれば、人々の豊かな人生、生きがいと言われるような、人類であれば普遍的な欲求を満たすこと。そこに寄り添うようなこと。観光でいえば宿泊体験やツアープラン、滞在プランが考えられると思います。
ウェルネスツーリズムは、知りたいと思って検索しても、教科書のようなものはありません。見つかるのは、エステやスパなど海外のラグジュアリーな感じのもの。しかし今、私たちが目指すべきは、海外はこうだ、と言われても動じずに発信していけるような“日本型”ウェルネスツーリズムです。

荒川雅志教授国立大学法人琉球大学 国際地域創造学部/観光科学研究科 教授。日本の大学で初の「ヘルスツーリズム論」専門科目を開講。ヘルスツーリズム、ウェルネスツーリズム研究の第一人者。
甲斐原今回、中部山岳国立公園南部地域の特性を生かしたツーリズムを考えたときに、ウェルネスツーリズムだと感じました。さまざまなアクティビティや、それを楽しんだ後に癒される温泉もある。そこでまずはウェルネスという視点でこのエリアを見直そう、可能性を掘り起こそうということで調査を始めました。
森川個性や歴史を生かした地区ごとの発信はどうしても“点”になってしまう。私たちの役割は、コーディネーター、マネージャーという意識で、エリアを横断するような中継役を担うことです。私にとってウェルネスツーリズムというのは新しい概念でしたが、その一方で、アドベンチャーツーリズムやエコツーリズム、最近ではサスティナブルツーリズムというのもあります。いろいろな見せ方がある中で、どのような視点を持つべきなのかは悩ましいところです。

森川政人さん環境省中部山岳国立公園管理事務所所長。2009年入省、2020年から現職。東京・練馬出身で、幼いころはトンボ採りにはまっていたという。「ある日、採れなくなっちゃったことがショックで、そのとき初めて環境を意識しました」
荒川そういう悩みはよく聞くし、よく分かります。答えになっていないかもしれませんが、そもそもウェルネスはある種、業界用語とも言えます。プレイヤーや事業者はちゃんと理解しないといけませんが、それをそのままお客さんに、例えばツアー名に付けて出すほうがいいのかどうか。戦略的に出す、出さない、両方あっていいと思いますが、あえて出さなくても、ウェルネスといえるような体験があって、結果、伝えたいことが伝われば十分なのではないでしょうか。
甲斐原コロナ禍を機に、旅行を娯楽やレジャーの概念だけではなく、心身の健康に寄与する、もっと日常生活と結びついた要素だと捉える人も増えました。自分を見つめ直すことの重要性に気付いてもらう。そういう見せ方を、プレイヤーや事業者の皆さんに賛同してもらえるかどうか。今回の調査は、ポテンシャルと共に、そういった気付きを促したいということも、内在的な目的としてはあります。

甲斐原さなえさん環境省中部山岳国立公園管理事務所利用企画官。森林セラピストの資格も持つ。「小学生の頃、家族旅行で訪れた上高地、穂高連峰、キラキラ光る梓川の情景を今でもはっきりと覚えています」
森川旅をしている人に対して、先ほど先生がおっしゃった、人間の本質的な欲求である豊かな人生、生きがいということを見つけて生きていきたい、というところに寄り添うようなものを提供する。それを包含する最上段にあるのがウェルネスというキーワードになりそうです。
荒川エステ、スパ、ヨガ、温泉といったものも間違いではないですが、それだと、先ほど挙げた少し古い、海外のラグジュアリーなものに近づいてしまう。短絡的なコンテンツにとどまらず、間口をできるだけ広く捉えたいですね。日本は自然と共生してきた国家であり、全国津々浦々、ウェルネスツーリズムに有利な資源があります。ウェルネスコンテンツも無限にあるはずです。環境と自分の体内環境の整理保全という、皆が目指すべきウェルネスツーリズムというのは、今ここからスタートしていくのではないでしょうか。ワクワクしますね。
地域の人たちとつくる「つながりツーリズム」
荒川例えば、旅行で訪れた人が、厳しい環境に身を置いて、自然と対峙する。それを1年スパンで繰り返すことで人生になっていく。今回、実際にこの地域に魅力を感じ、移住したり事業を立ち上げたりしたという人と出会って、資源の価値は人が寄り添うことで輝くということを実感しました。言ってみれば、日本各地にこういった自然があり、資源は豊富ですが、そのポテンシャルを引き出せるかどうかは、語る人がいるかいないかが鍵になってきます。
森川中部山岳国立公園南部地域は、南北に連なる北アルプスを挟んで、西は日本海側の気候で関西・中部文化圏、東は太平洋側の気候で関東文化圏という特性があります。東京出身の私にとっては、この違いがとても面白い。地形が生んだ人間の文化の違いなのかなと思っています。上高地を中心に、拠点と呼べる場所がこの狭い範囲に数多く集まっていることにもポテンシャルを感じます。

荒川あらゆるプレイヤーが参画でき、地域住民とフラットな関係で来訪者をもてなすという“日本型”のウェルネスツーリズムは、まちづくり、地域づくりにもつながります。その事例として挙げられる地域は、今はまだなくて、地元の皆さんと「地域ファースト」で取り組むことができれば、そこがウェルネスツーリズムの先進地になると思います。
甲斐原先進地と言われるのは日本では沖縄だと思っていますが、地域が主体となってやっていくという意味では、沖縄のウェルネスツーリズムとはまたちょっと違うスタイルということですね。
荒川私は最近、ウェルネスツーリズムは「つながりツーリズム」と言っています。ポストコロナ時代、世界中が物理的なつながりを持てなくなっているところで、逆にそれを求めている。自然、地域、そして人とのつながりを感じられるコンテンツやサービスは、ウェルネスツーリズムの中身になるし、つながり人口というところまで含めると、観光という枠を超えるものになっていきます。
森川国立公園は国内に34カ所あるのですが、ここは山岳の国立公園としては随一だと思っています。それは、地域の皆さんも同じ思いのはず。だからこそ、一緒に、いろいろなことに挑戦していきたい。その一つとして、まずは皆さんにウェルネスというものを知ってもらうことからスタートしたところです。
人と自然が共生しているというスタイルを自分事化して、地域のスタイルとは何かを考え、それを来訪者にも提供していく。これを突き詰めていけば、ウェルネスツーリズムが目指すものと自然と重なっていくのではないかと思います。
基調講演・パネルディスカッション
中部山岳国立公園南部地域におけるウェルネスツーリズムの今とこれから
2022年3月7日に、荒川教授に登壇いただき、「ウェルネスツーリズム・今とこれから」をテーマにした基調講演とパネルディスカッションを開催しました。当日の様子はこちらでご覧いただけます。