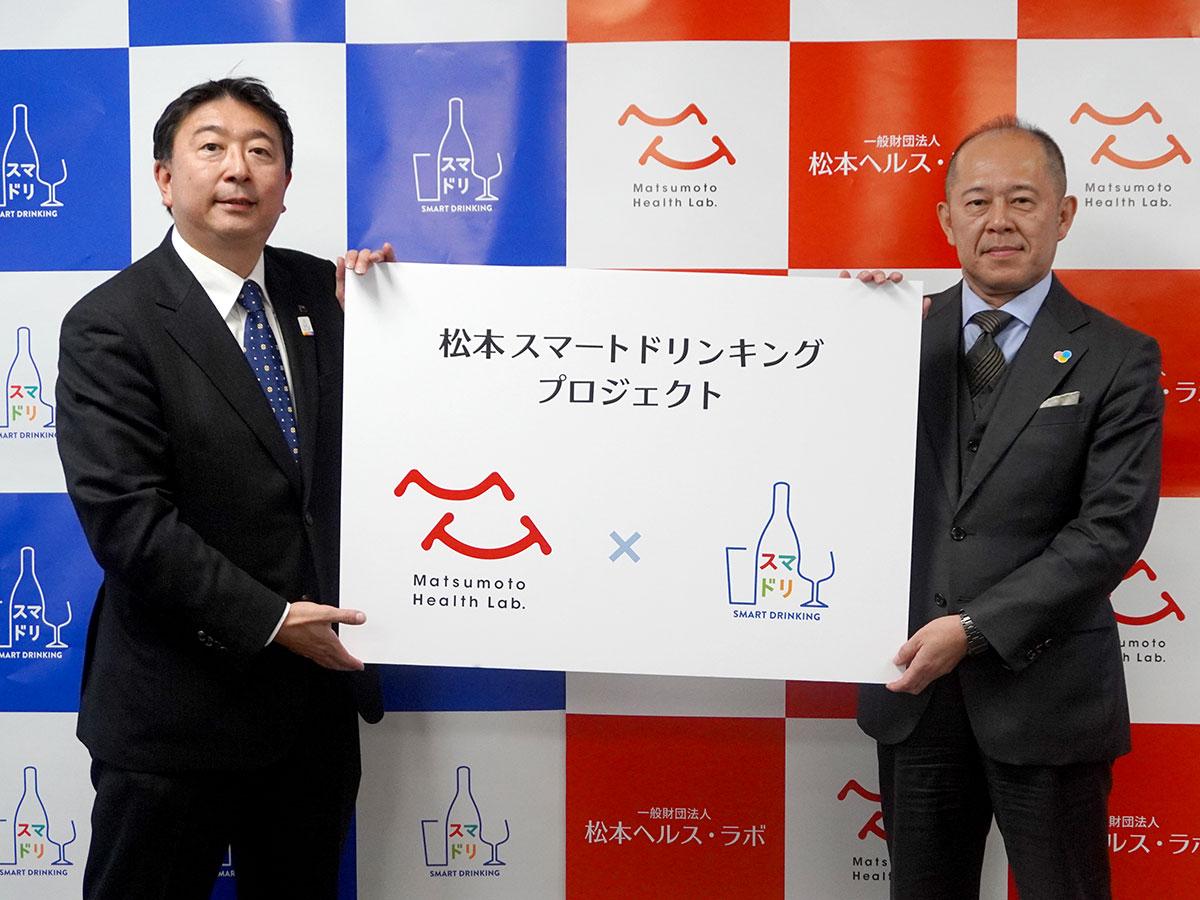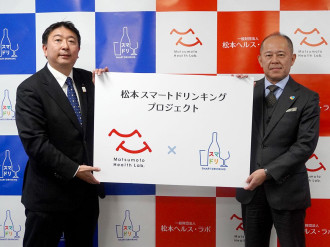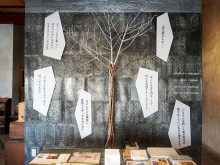松本で「工芸の五月」 市内40カ所、多彩なイベントで手仕事の魅力伝える

工芸にまつわるさまざまな企画やイベントを展開する「工芸の五月」が現在、松本市内の美術館、博物館、ギャラリーなど約40カ所で行われている。
松本市美術館(松本市中央4)では、「異形の宴(うたげ) あそび心の蒔絵(まきえ)」(5月6日まで)を開催。漆芸家・故若宮隆志さんが2004(平成16)年に立ち上げた石川県輪島市の漆芸職人集団「彦十(ひこじゅう)蒔絵」の作品、約50点を紹介する。漆の技法を用いて、「玉虫厨子(たまむしのずし)」など国宝を見立てた作品をはじめ、青いグラデーションをベースに魚を蒔絵で描いた三線や、蜷川べにさんとコラボしたエレキ三味線なども展示。青銅器やたい焼き、工具など、本物と見間違うような異素材を漆芸で表現した作品もあり、実物の金づちと重さを比べられるコーナーも設ける。
同団体は現在、20代から60代の職人約20人が所属。分業制でそれぞれの技術を持つ職人を組み合わせて制作活動を行っている。「工芸の五月」実行委員長の伊藤博敏さんが昨秋、展示を通じて以前知り合った若宮さんに企画展を持ちかけた。同展の作品は、昨年1月の能登半島地震で被災した工房から救い出したものを中心に、昨夏以降に取り組んできた新作も含まれている。今年2月に若宮さんが亡くなり、意思を引き継ぎ高禎蓮さんが代表に就いた。高さんは「輪島の漆芸を後世に継承するためにも、多くの人に高い技術と多彩な魅力を知ってもらいたい」と話す。
信毎メディアガーデン(中央2)では、子ども用の椅子を展示する「はぐくむ工芸 子ども椅子展」(5月6日まで)が行われている。県内在住を中心に、木工作家やデザイナー30人が手がけた約50脚の椅子を用意。シンプルなスツールやベンチのほか、動物の形をしたユニークなものもある。
ほかに、湧き水と工芸をテーマに町歩きを楽しむ「建築家と巡る城下町みずのタイムトラベル」(10日・11日、17日・18日)や、クラフト作家の器で酒を楽しむ「ほろ酔い工芸」(17日、三代澤酒店)なども。メインイベントの「クラフトフェアまつもと」(24日・25日、あがたの森公園)は、約260組が出展を予定する。
「工芸の五月」は今年で19回目。毎年5月を「工芸月間」として、工芸にまつわる企画を市内各所で展開している。現在、オフィシャルガイドブック(550円)を市内各施設・店舗・ウェブサイトで販売するほか、「松本ブルワリー」では「工芸の五月限定オリジナルビール」を提供している。
5月31日まで。